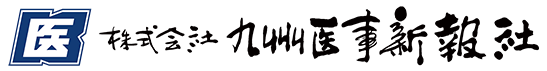にのさかクリニックバイオエシックス研究会 第37回米沢ゼミ
いのちに寄りそう道標をさがして
―明治(漱石・子規・啄木)の時代の病と看護から―
ひらまつクリニック 鐘ケ江 寿美子
長寿社会の今、社会は制度化、病院化し、介護化してきたと評論家・米沢慧氏はセミナーをはじめた。2018年は明治維新150年。この間、予後余命は50年から人生80年に飛躍。ケアに相当することばは介抱・看病を経て、看護、介護とひろがり、医療や介護に関する職種は専門分化している。セミナーでは米沢氏の新著「看護師のための明治文学 漱石の時代の介抱・看病・看護」(日本医療企画 2018)より、明治の文豪が自らの闘病生活より視(み)た、介抱や看護について紹介された。
1. 正岡子規(1867―1902)の病いと看病 「病床六尺」
脊椎カリエスを患った子規は寝床(病室)である書斎にて著した「病床六尺」にて苦痛と煩悶の中で、「病人の苦楽に関係する問題は介抱の問題である」と説いた。子規は病気の介抱に精神的と形式的の2様があり、「精神的介抱」は看護人が同情をもって病人を介抱すること、「形式的介抱」は病人をうまく取り扱うこと(例、服薬・入浴の介助、環境整備)といった。そして、病人の介抱は医師の助手ではなく、病人を慰めることであり、彼を介抱した母や妹の細やかな気遣いにあるように、介抱の「精神的同情(共感)」を重んじた。これは患者への尊敬の念、人類愛、スピリチュアル・ケアを含むものと考えられる。
2. 夏目漱石(1867―1916)の病いと看護 「則天去私」
漱石43歳、保養先の修善寺にて胃潰瘍による吐血で「人事不省」に陥った「30分の死」を体験し、「則天去私」(私情を捨て去って天の心にしたがう)へと舵をきったといわれている。
漱石は職務にあたる医師や看護師に接し、「彼らの義務の中に、半分の好意を溶き込んで、それを病人の眼から透かして見たら、彼らの所作がどれほど尊とくなるか分からない。病人は彼らのもたらす一点の好意によって、急に生きて来るからである」とあらわし、看病に対する感謝の念を「自分に活力を添えた当時の感情を、余はそのまま長く余の心臓の真中に保存したいと願っている」と記した。また、漱石を看病した派出看護婦(現在の訪問看護師の原型)の様子が彼の文章より知ることができ、興味深い。
3 .石川啄木(1886―1912)の病いと看護 「入院体験と看護婦」
啄木は肺結核のため東大附属病院に施療患者として入院した。死後に発表された詩集「哀しき玩具」に彼の体験や看護婦への関心が詠まれている。
- ドア押してその足出れば、
病人の目にはてもなき
長廊下かな。 - 夜おそく何処やらの室の
騒がしさは、
人や死にたらむと、
息をひそめる。 - 脈をとる看護婦の手の、
あたたかき日あり、
つめたく堅き日のあり。 - 看護婦の徹夜するまで、
わが病ひ、
わるくなれとも、
ひそかに願える。
明治時代の難治性の病に、研ぎ澄まされた観察眼と感性をもって向きあった、子規、漱石、啄木が求めた看護は、「いのちに寄りそってほしい」という思いであると米沢氏は解説した。そして、「いのち」とは「生・老・病・死」といういのちのできごとを指し、「いのち」の物語に手をさしのべ寄りそうことが「看護の本源」と文豪たちが問いかけているように見える。「看護」という概念は抱擁・介抱、看病、看取りをとりこんだ「いのちことば」であるとセミナーを締めくくった。
自らの病に向き合う人は偉大な「臨床の師」であると、明治の文豪にあらためて教えられた思いである。