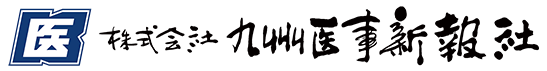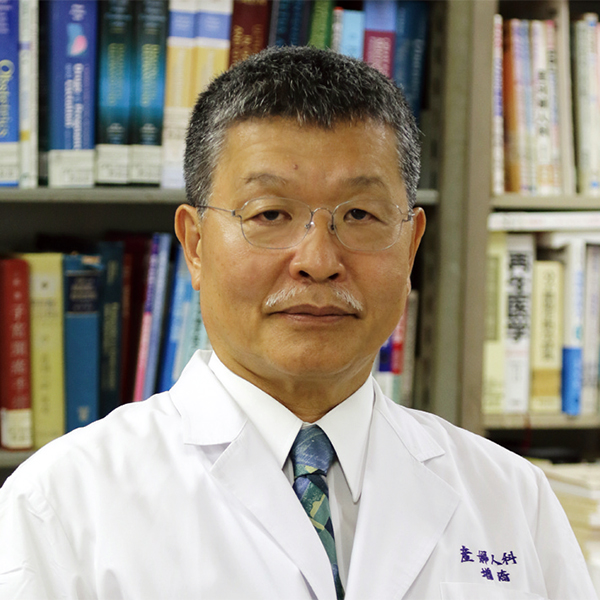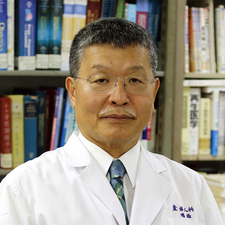夏目家のお産
日本が鎖国から解放され、それまでの日本人の価値観が、西洋から流入した哲学によって危機に瀕したとき、新しい日本語(口語体)で古い日本人の魂を伝えたのは、ドイツ帰りの森鷗外とイギリス帰りの夏目漱石の二人であった。だが家庭人としての二人には別の顔つきがあった。妻があり、子をなした。
明治38年も暮れのことである。『我輩は猫である』を発表して時の人となっていた漱石の家には、弟子を称する者たちが陸続と訪れるようになった。だが当時、妻の鏡子は四女を懐胎しており、家に押し掛ける弟子の世話などできそうにない。それで木曜日だけを面会日と定めた。しばらくは平和な日々が続いたが、ある日の夜明け前、ついに本格的な陣痛がやってきた。医者や産婆は間に合いそうにない。鏡子はやむなく漱石を起こし、夫だけを相手に出産することを決意する。「もうあなた産まれそうです」。漱石の手につかまって、うんうん言っているうちに、とうとう出産してしまった。その場には、鏡子と漱石と赤ん坊しかいない。鏡子は、生まれたばかりの赤ん坊の世話を漱石に頼むほかなかった。鏡子が「脱脂綿で赤ん坊の顔をおさえて下さい」と言うと、漱石は「よしきた」と赤ん坊の顔をおさえる。なかなかの名コンビである。こうした夫婦の共同作業によって、四女の愛子はこの世に生を受けたのであった。夏目漱石・鏡子夫妻はおおよそ2年おきに妊娠し、2男5女を授かっている。つまり夫婦仲は、巷間で取り沙汰されるほどには悪くなかったのであろう。
漱石は周期的に精神に異常をきたしたが、この頃は小康の時期であり、比較的やさしい父親であった。だがいつもの漱石は、子供達には恐ろしい父親であったようだ。次男の伸六は『父・夏目漱石』において、「私たち兄弟の中で、少しも父をこわがらなかったのは愛子だけで、父はこの姉を一番可愛がっていた」と書いている。愛子が6、7歳の頃、「愛子さんはお父さんの子じゃない。弁天橋の下で拾ったのだ」と漱石が言うと、愛子は漱石に向かって言ったそうだ。「あらいやだ。わたしの生まれたときに脱脂綿で私をおさえていたでしょ」。
以上は、主として夏目鏡子の『漱石の思い出』から引いた話である。漱石も鏡子も世間からは散々様々に悪口を言われたり書かれたりしたが、普通の家庭と同じように、夫婦喧嘩もすれば仲の良いときもあった。娘を自分自身で取り上げた漱石は、分娩の崇高と神秘を思い知り、妻に対する愛情は否応なく深まったに違いない。本年が皆様にとって良い年でありますように。