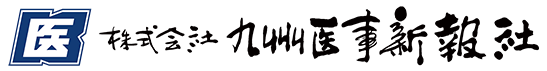社会福祉法人恩賜財団 済生会宇都宮病院 小林 健二 院長(こばやし・けんじ)
1976年慶應義塾大学医学部卒業。
同外科学教室、済生会宇都宮病院救命救急センター所長、副院長などを経て、
2016年から現職。済生会宇都宮病院看護専門学校長を兼任。
今年、設立77年目を迎える済生会宇都宮病院。栃木県で初の救命救急センターを設置した歴史を持ち、急性期病院として地域と共に歩んできた。宇都宮市の高度医療・地域医療を支える役割は大きい。昨年、ICUや手術室の拡充を行うなど、宇都宮市の基幹病院としての存在感が高まる中で、病院内の改革も進んでいる。
―救急医療と高度医療という両面を担っています。
一番の特徴は「高度医療と救急医療」を併せ持った総合病院である、ということです。昨年、ICUの機能を拡充。ハイブリッド手術室や、手術支援ロボットである「ダビンチ」を導入し、高度医療機関としての設備を強化しました。実際、今年の救急患者受け入れ数は昨年を上回るペースで推移しています。