地域において大きな課題となっている老年精神医学について考える「第35回 日本老年精神医学会」が6月13日(土)・14日(日)に米子コンベンションセンターで開かれる。鳥取県で初の開催、脳神経内科医が大会長を務めるのも26年ぶりという。大会長の浦上克哉・鳥取大学教授に今回のポイントを聞いた。
第35回日本老年精神医学会 地域を支える老年精神医学
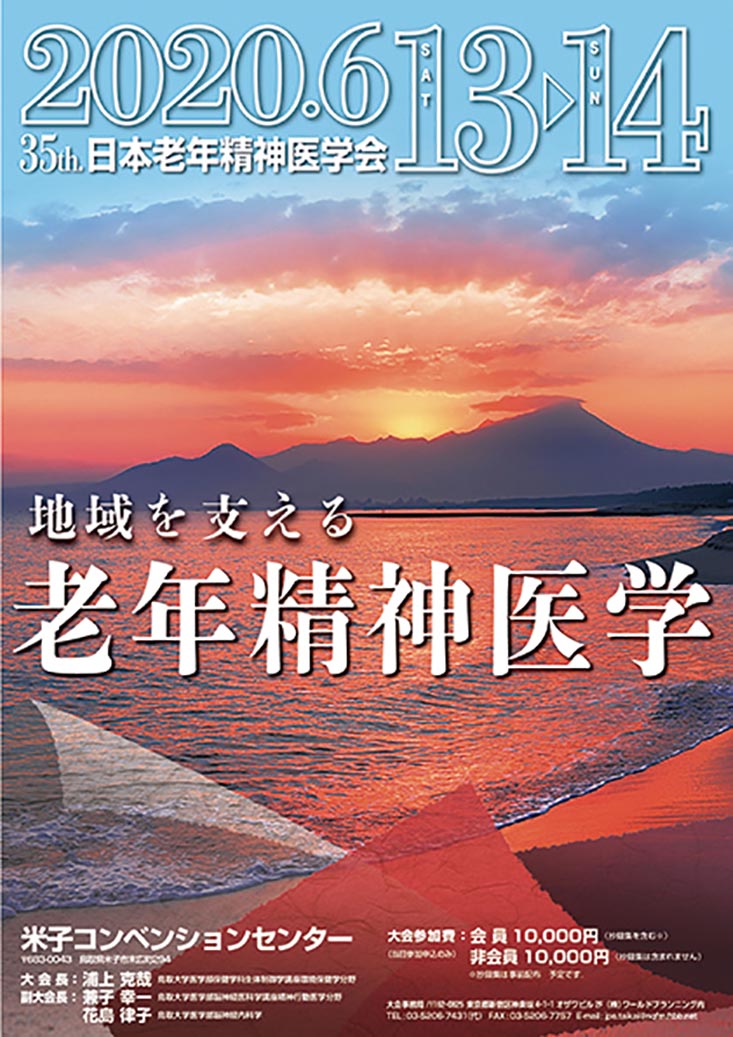
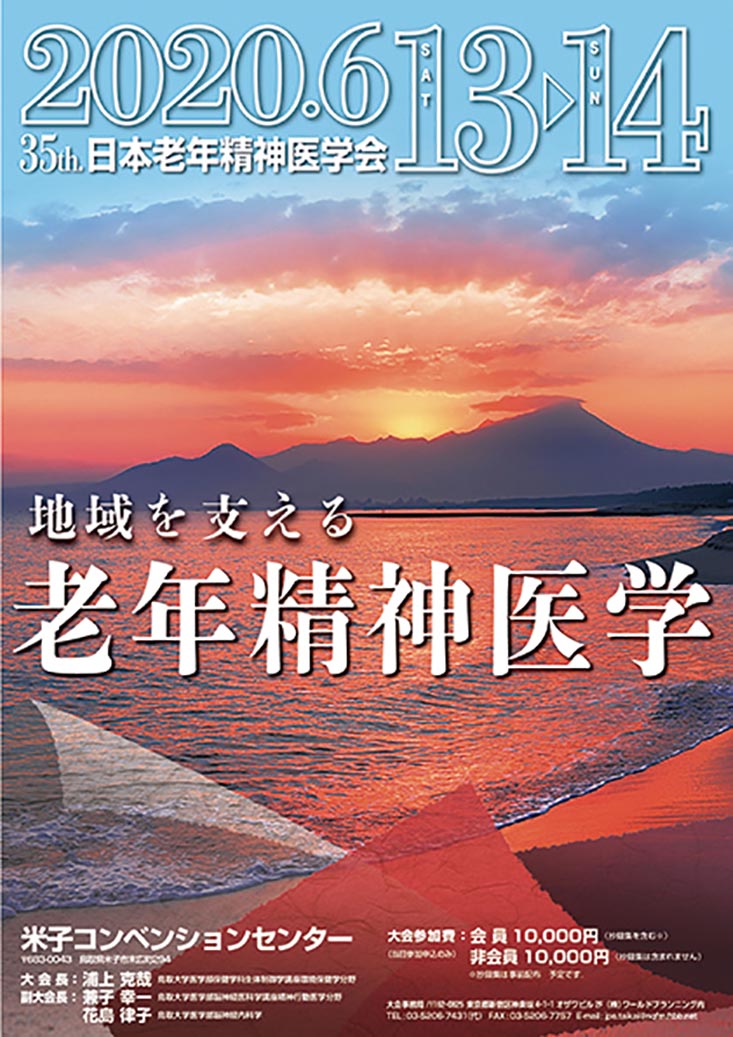
地域において大きな課題となっている老年精神医学について考える「第35回 日本老年精神医学会」が6月13日(土)・14日(日)に米子コンベンションセンターで開かれる。鳥取県で初の開催、脳神経内科医が大会長を務めるのも26年ぶりという。大会長の浦上克哉・鳥取大学教授に今回のポイントを聞いた。