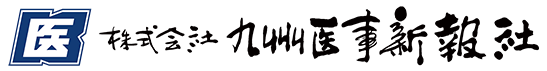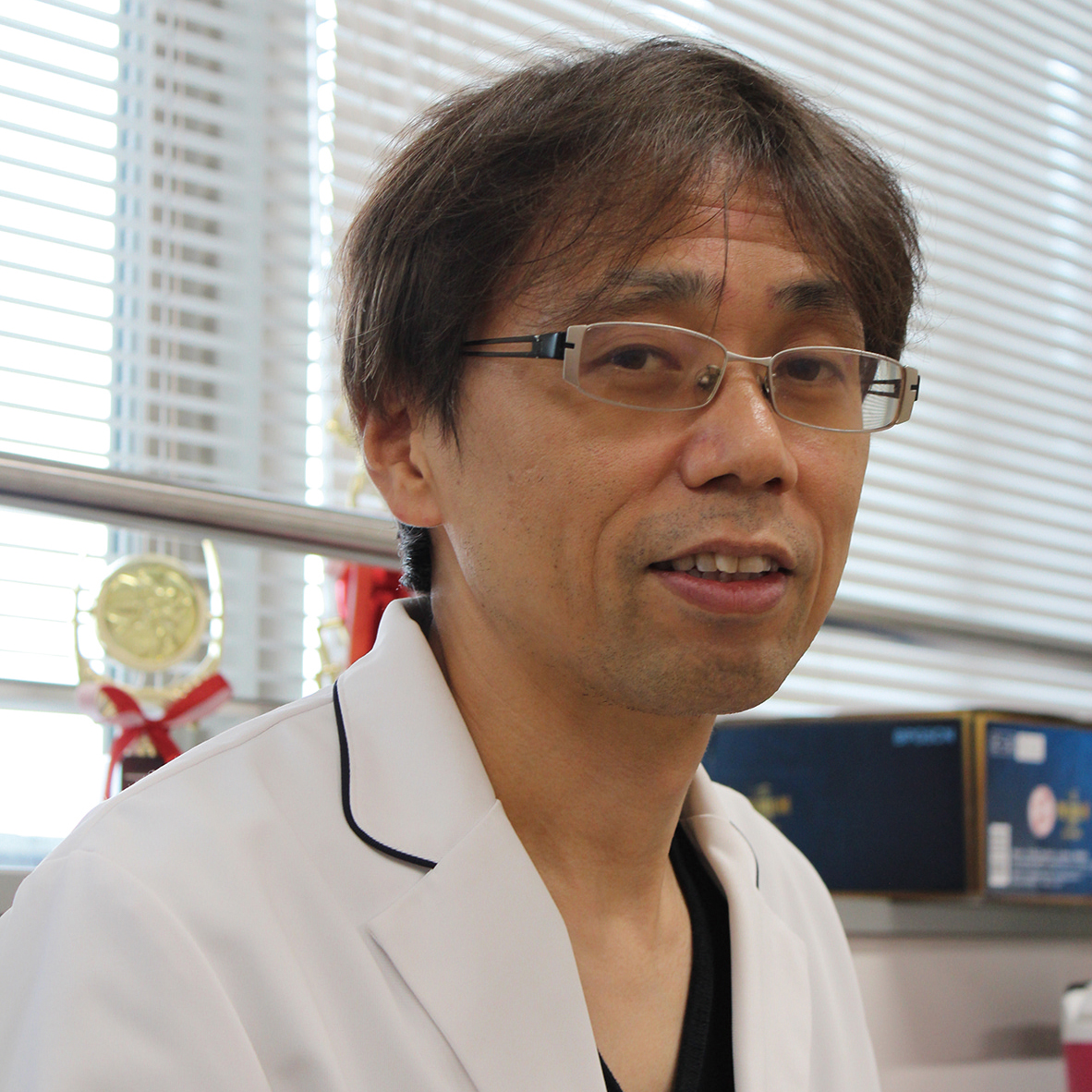熊本大学大学院 生命科学研究部 放射線診断学分野
中浦 猛 講師(なかうら・たけし)
1997年熊本大学医学部卒業。JCHO天草中央総合病院放射線科、
天草地域医療センター放射線科部長などを経て、2015年から現職。
熊本大学大学院画像診断解析学寄附講座特任講師兼任。
熊本大学放射線診断学分野は、IVR(画像下治療)で数多くの治療実績を持ち、画像診断においては、AI(人工知能)を利用した研究が盛んだ。AIの医療への応用は非常に早いスピードで進んでいるが、放射線診断学分野では、どのように活用されているのか。中浦猛講師に聞いた。
―医局の特徴は。
医局と関連病院に派遣する医師を含め、約100人の医局員が在籍。画像診断とIVRを中心に、研究や診療を行っています。