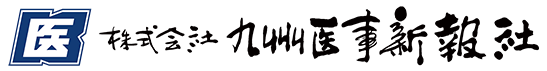新型コロナウイルス感染症(COVID―19)拡大の影響で、オンライン診療が関心を集め、広がりを見せている。厚生労働省は4月、閣議決定の同感染症緊急経済対策を受けて、電話や情報通信機器を利用する「オンライン診療」を、初診も含めて可能とする時限的・特例的緩和策を打ち出した。一方、日本医師会は「今回は非常事態の下、感染防止、医療崩壊を避けるための特例で、収まり次第、対面診療に戻すべきだ」と主張している。
感染拡大に伴い希望機関・患者が増加
厚労省は同省サイトで、電話や情報通信機器による診療に対応する医療機関リストを公開。すでに1万5000以上の医療機関が掲載されている。
この続きをみるには