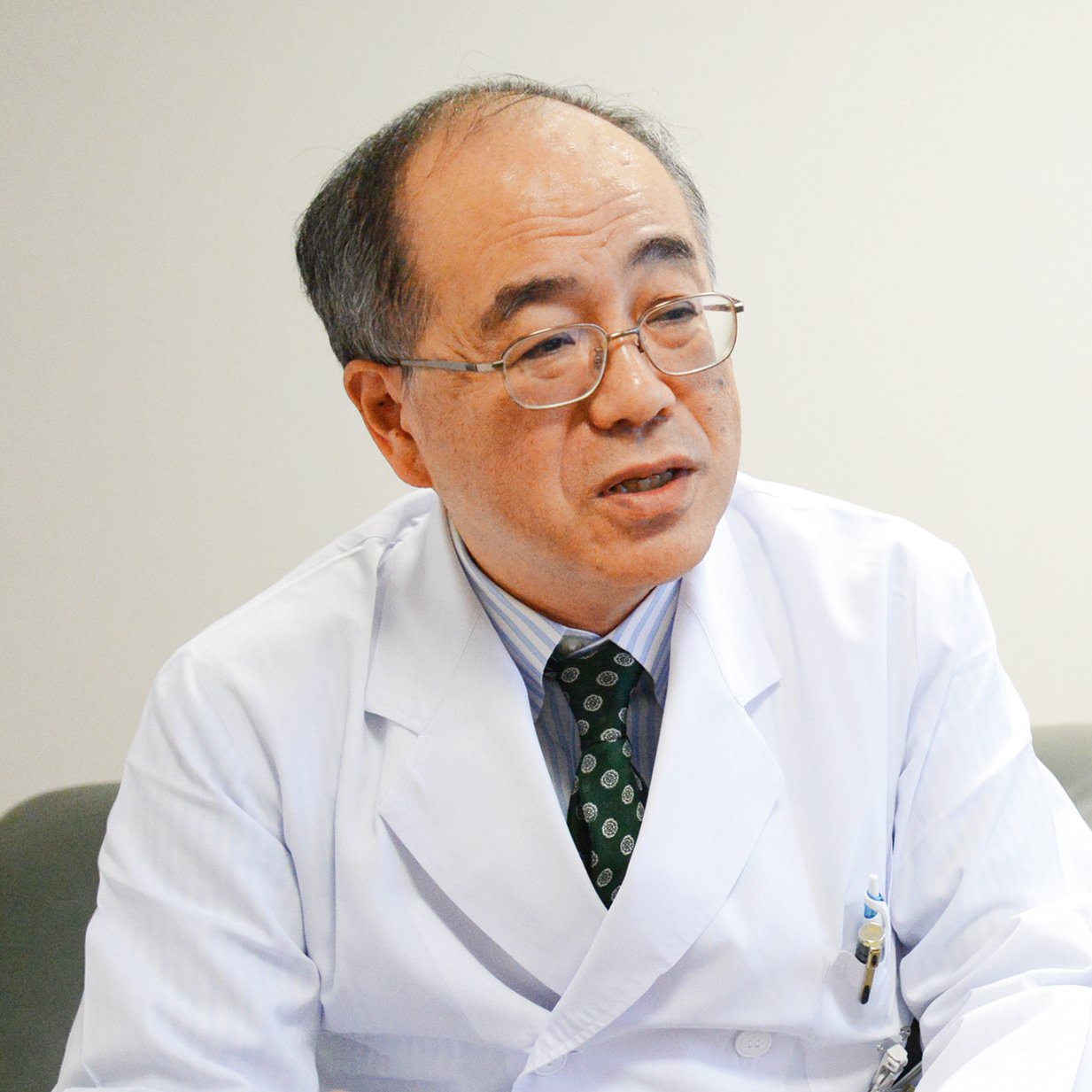地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
荒木 康之 病院長(あらき・やすゆき)
1980年岡山大学医学部卒業。
国立病院四国がんセンター(現:国立病院機構四国がんセンター)、
岡山大学医学部附属病院(現:岡山大学病院)第一内科、広島市民病院副院長などを経て、
2012年から現職。
広島市中心部に位置し、地域の高度急性期、急性期の医療を支える広島市立広島市民病院。2018年度の手術件数が、開院後初めて1万件を突破した。地域がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センター、災害拠点病院。多くの役割を担いながら、存在感を高め続ける。
―手術件数が1万件を突破しました。
1万76件の手術を実施。目標としていた1万件を超えることができました。ハイブリッド手術室を含む手術室の増設、次の手術までのインターバルの短縮など、病院全体で取り組んだ成果だと思います。