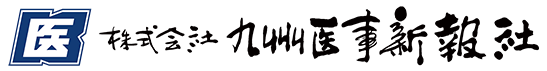島根大学 医学部内科学講座(内科学第二)
石原 俊治 教授(いしはら・しゅんじ)
1988年島根医科大学医学部(現:島根大学医学部)卒業。
島根県立中央病院、島根大学医学部内科学講座(内科学第二)准教授、
同附属病院IBDセンター長などを経て、2019年から現職。
研修医時代の患者との出会いが原点となり、炎症性腸疾患に長年取り組んできた。島根大学医学部附属病院IBD(炎症性腸疾患)センターの設置にも尽力し、2019年8月に教授に就任。患者一人ひとりに向き合ってきた石原俊治教授に、今の思いを聞いた。
より難しい疾患に挑む
内視鏡を用いた消化器疾患の臨床と分子生物学を用いた病態解明の研究に取り組む島根大学医学部の内科学第二講座。石原教授を中心に、難病にも果敢に立ち向かっている。