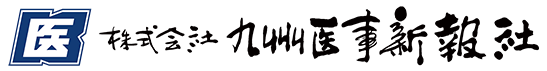地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター
土肥 直文 院長(どい・なおふみ)
1987年奈良県立医科大学医学部卒業。
総合大雄会病院、奈良県立医科大学救急医学助手、同第1内科学助手、
奈良県西和医療センター副院長兼循環器内科部長などを経て、2020年4月から現職。
奈良県西和医療圏の中核病院として、圏域約34万人に対し、高度で特色ある診療を提供している奈良県西和医療センター。2020年4月、院長に就任した土肥直文氏に、病院運営について聞いた。
コロナと戦い続ける
2020年5月下旬から同センター駐車場に、新型コロナウイルスの感染に不安を持つ住民の診察を行う、発熱外来クリニックを開設している。診察室4室、救急処置室2室、レントゲンやCTなどの医療機器のほか、スタッフルーム、事務室、PPE着脱室なども備え、1日20人以上の診察が可能となった。