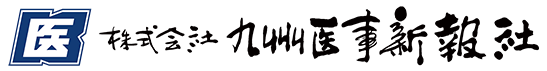独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 久保 俊英 院長(くぼ・としひで)
1984年岡山大学医学部卒業。岡山大学医学部附属病院(現:岡山大学病院)小児科、
岡山市立市民病院小児科部長、岡山医療センター特命副院長などを経て、
2019年4月から現職。
2003年に小児科医長として着任した久保俊英医師が、今年4月に院長に就任した。長年、特に成長障害を専門に取り組んできた久保院長に、これまでの事例を踏まえ、小児医療との向き合い方や今回の就任に当たっての抱負を伺った。
―成長障害がご専門ですね。
小中学校では、学校教育法に基づいて身長と体重の計測を毎年行っていますが、標準の成長曲線の一番端の枠外に出てしまう子や、枠内であっても通常の成長パターンと異なる動きを見せる子がまれにいます。