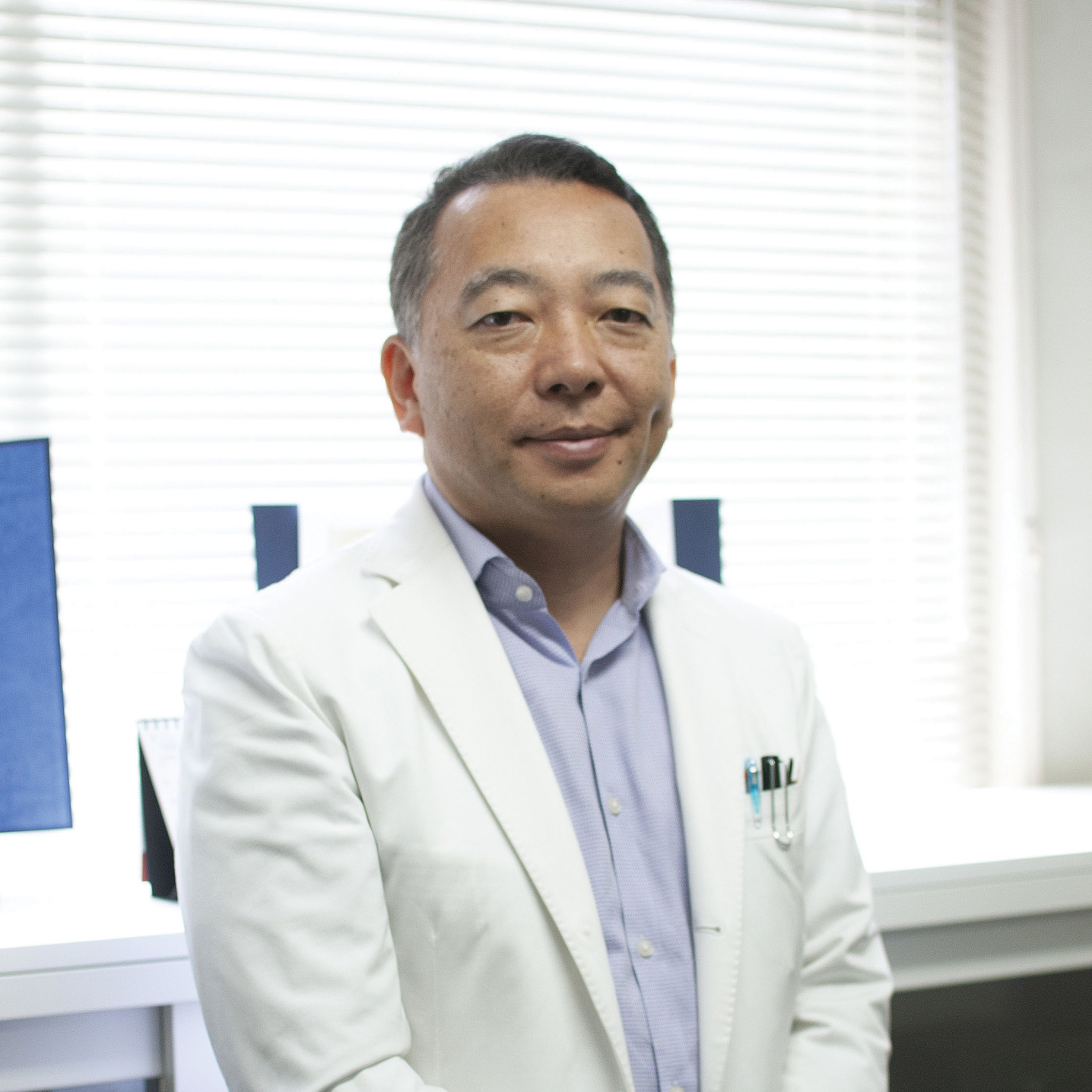東京大学医学部眼科学教室 相原 一 教授(あいはら・まこと)
1989年東京大学医学部卒業。米カリフォルニア大学サンディエゴ校
緑内障センター留学、東京大学医学部眼科学教室准教授、
四谷しらと眼科副院長などを経て、2015年から現職。
現在、日本で失明原因の第1位となる緑内障。緑内障治療の鍵となる眼圧のメカニズムがいまだ解明されない中、研究を続ける眼科界のトップランナー、相原一教授に話を聞いた。
―東京大学医学部眼科学教室の特徴や取り組みは。
当教室は、昔から眼科をリードしてきましたが、特に、多分野にわたってバランスよく患者さんを診ることができるところが特徴です。