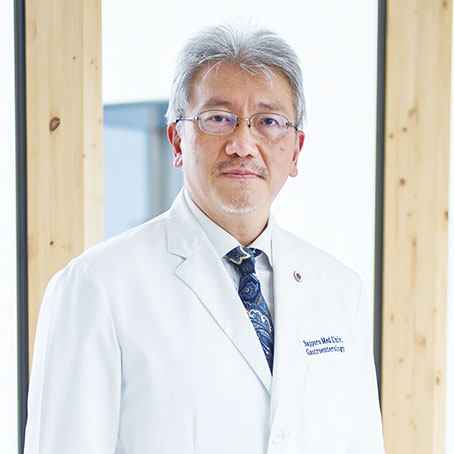札幌医科大学医学部 消化器内科学講座
仲瀬 裕志 教授(なかせ・ひろし)
1990年神戸大学医学部卒業。
日本学術振興会特別研究員、米ノースカロライナ大学消化器病センター、
京都大学医学部附属病院内視鏡部などを経て、2016年から現職。
札幌医科大学附属病院消化器病センター長兼任。
全国的な内科系講座の臓器別再編の流れに伴い、札幌医科大学の現在の消化器科内科学講座も、2016年に、これまで内科を総合的に担ってきた第一内科学講座から消化器に特化した名称となった。仲瀬裕志教授に、再編された教室の現状と、炎症性腸疾患の研究について聞いた。
─再編効果は。
私が医者になったばかりの頃と比べ、現在の内科診療は膨大な知識量を必要としており、また行政の方針もあって、専門性の高いドクターの育成を目指す流れが加速しています。