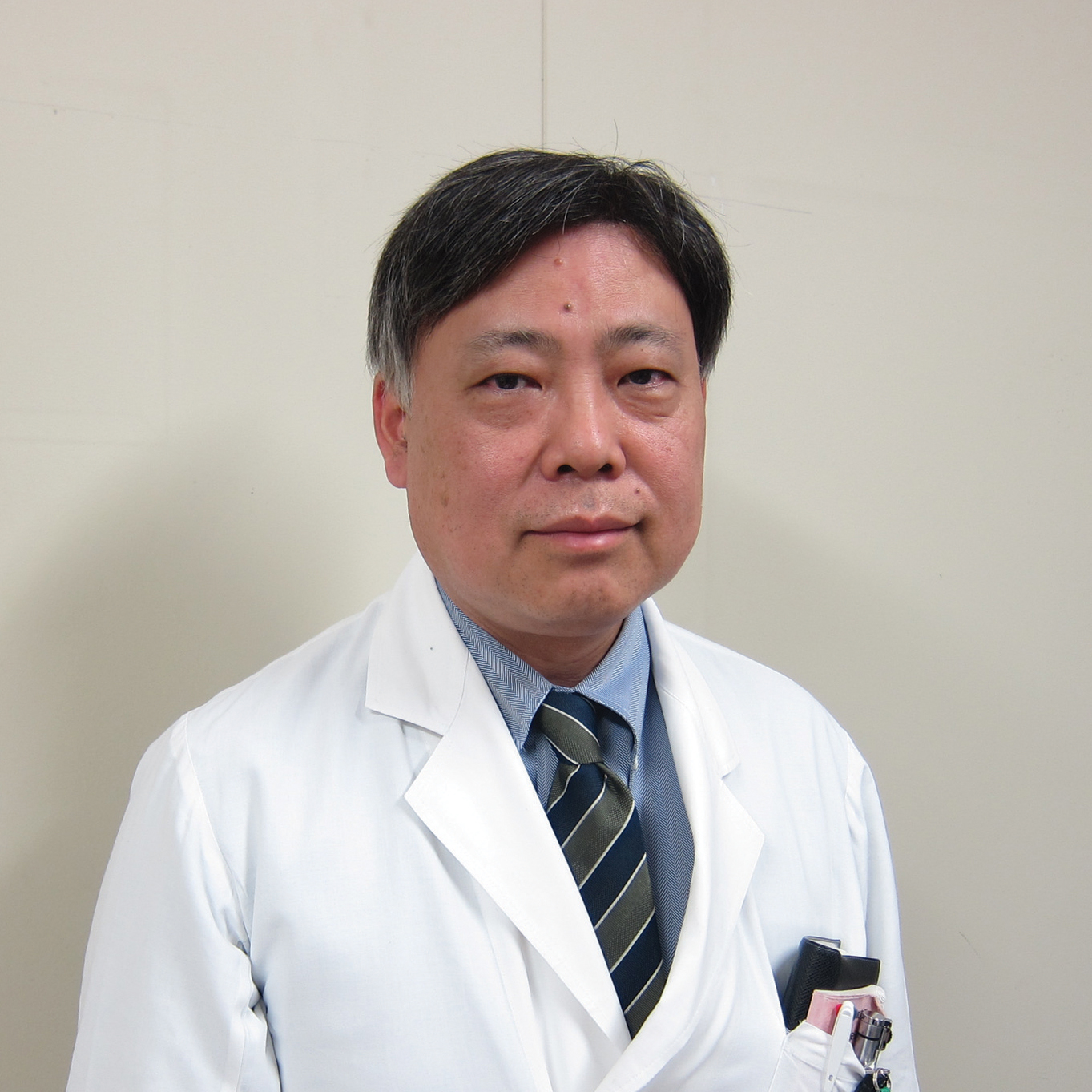福岡大学医学部 眼科学 内尾 英一 主任教授(うちお・えいいち)
1985年九州大学医学部卒業。横浜市立大学眼科講師、
同医学部附属市民総合医療センター眼科助教授などを経て、2005年から現職。
目の表面に花粉などのアレルゲンが付着することで起こる「アレルギー性結膜疾患」。年々増加傾向にある眼科アレルギー疾患について、日本アレルギー学会専門医、指導医の内尾英一主任教授に話を聞いた。
―アレルギー性結膜疾患について教えてください。
アレルギー性結膜炎と春季カタル、アトピー性角結膜炎、巨大乳頭結膜炎の四つの病気をアレルギー性結膜疾患と総称しています。軽症型のアレルギー性結膜炎に対し、残り三つは重症型です。