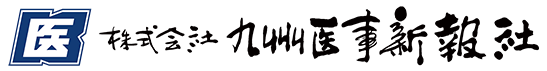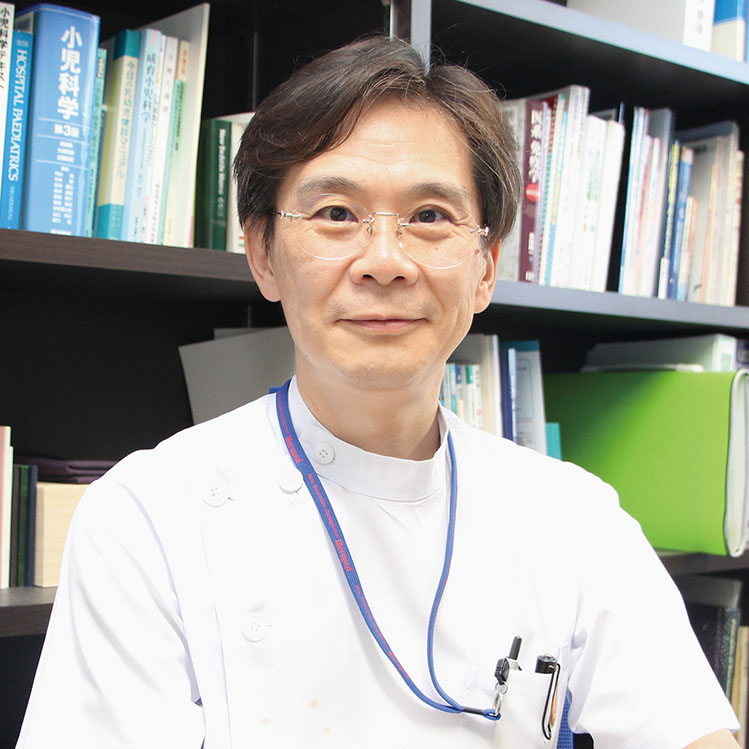鳥取大学医学部 周産期・小児医学分野
難波 範行 教授(なんば・のりゆき)
1992年岡山大学医学部卒業。大阪大学大学院医学系研究科小児科学講師、
JCHO大阪病院小児科診療部長などを経て、2019年から現職。
戦後間もなくから地域の小児医療を守り続けてきた鳥取大学医学部周産期・小児医学分野。2019年に教授として就任した難波範行氏は、明確なスローガンを掲げて医局運営を指揮し、同時に大学病院内におけるワークライフバランスの推進にも力を入れている。
―医局の特徴は。
1946年に開講し、県内および山陰地方の小児医療を支えてきました。もちろん現在もその役割は変わらず、「すべての子どもに最善の医療を」という目標のもと、地域内で小児医療を完結させるために日々精進しています。