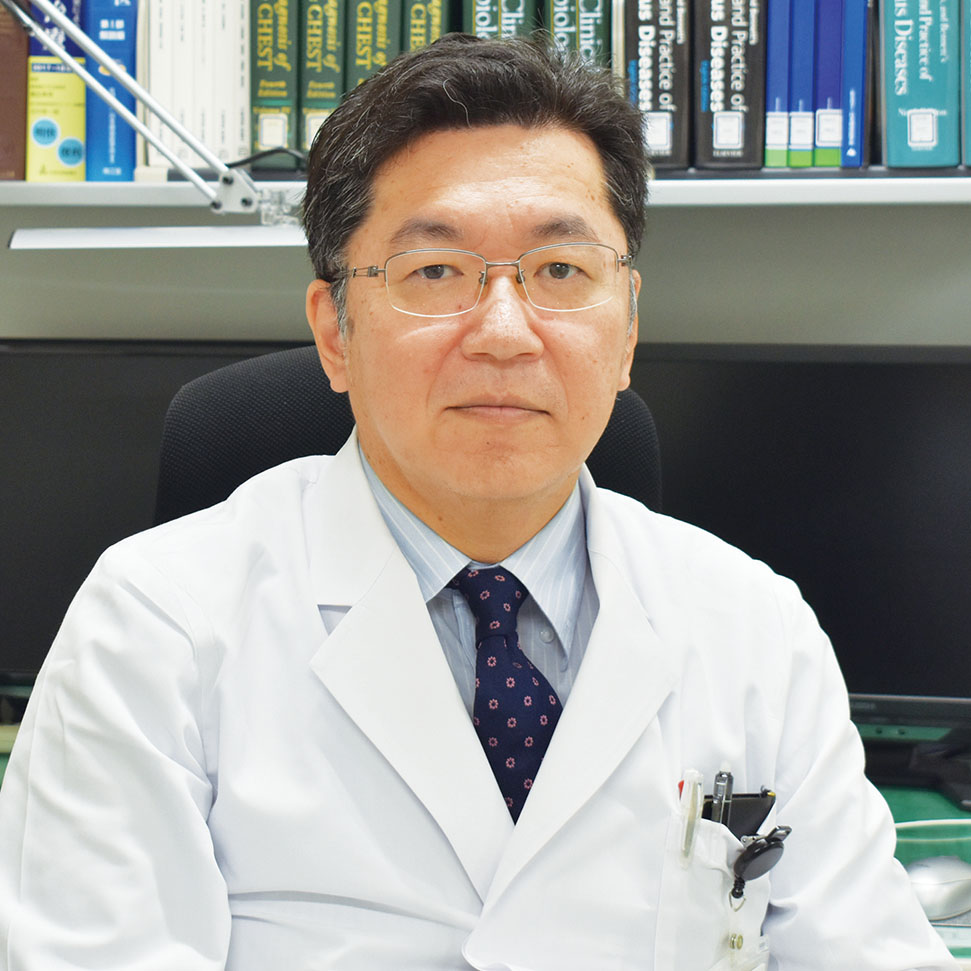大分大学医学部 医療安全管理医学講座
平松 和史 教授(ひらまつ・かずふみ)
1987年大分医科大学医学部(現:大分大学医学部)卒業。米国立衛生研究所、
大分大学医学部附属病院医療安全管理部・感染制御部診療教授などを経て、2017年から現職。
同大学医学部附属病院医療安全管理部長、同感染制御部長、同副病院長兼任。
高度化、複雑化する医療現場で起こりがちなエラーをどのように防ぐか。大分大学医学部附属病院の感染制御部と医療安全管理部の二つの組織を統括し、医療安全管理学講座では学生に医療安全を教える平松和史教授に「医療の安全」の取り組みについて聞いた。