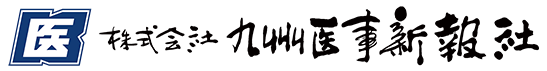『少子化対策 ―もう遅い』
戦後、第1次ベビーブーム(1947〜1949年:団塊の世代)と第2次ベビーブーム(1971〜1974年:団塊ジュニア)がみられたが、以後その再来はなく少子化の一途をたどっている。2018年人口動態統計の出生数は過去最少(91万8400人)になったとのことであるが、2016年に100万人を割り込んだまま、2019年には90万人を割るという。
一方、バブル崩壊(1991〜1993年)後の就職難が、いわゆる就職氷河期世代(1993〜2005年度卒業)を生み、それに労働者派遣法の改正(1996年)で年功序列の終身雇用制が廃止されたことも相まって、生活に希望が持てず、晩婚化・未婚化が進むこととなった。
当然、出生率への影響は大きく、それはまた、少子世帯を当たり前とする風潮を助長することにもなった。ちなみに、人口動態統計による2018年の婚姻件数は戦後最少となっている(58万6481組)。
ところで、国は今ごろになって、この就職氷河期世代の救済措置を言い出しているが、もはや、出生率向上には役立たない。
また、戦後、日本は6・3制義務教育を基軸とした新教育制度のもと高校・大学を増やし、急速に高学歴社会に誘導していったが、その帰結が今日の少子社会といえなくもない。というのも、かつて「貧乏人の子沢山」とやゆされる風潮があったが、それは、まだ、社会全体が貧しく、隣近所の助け合いが当たり前の、ある意味、相互扶助の協同的社会においてのことだったといえるわけで、産業構造が変化して社会が豊かになり、制度的に成熟した高学歴社会では、共働き世帯が一般化し、核家族化が進み、住環境の変化も相まって、隣近所のつながりが乏しくなってしまった結果、地域で子どもを育てるという意識が希薄になっていったことを挙げることができ、今となっては、この比喩は死語に等しいといえる。
だが、日本の出生率推移の分水嶺(れい)というか分岐点はバブル崩壊に重なると捉えることができるのではないか。だとすれば、バブル崩壊後の就職難に打つ手はなかったのか。打っていればどうなっていたのだろう。外圧に打ち勝って年功序列の終身雇用制を維持していればどうなっていたのだろう、との悔悟は残る。
このような少子化の必然性からみると、もはや、歴史を戻すことはできず、歯止め策も回復策も無いに等しい。残念ではあるが、少子化対策は、もう遅いと言わざるを得ない。