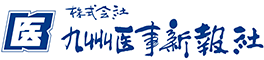第24回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会in久留米が2月4日と5日、久留米シティプラザ(福岡県久留米市)で開かれた。テーマは「いのちを受けとめる町づくり~日本のホスピスが忘れてきたもの~」。大会長は二ノ坂保喜・にのさかクリニック院長。実行委員長は齋藤如由・齋藤醫院院長。約2000人が参加した。
<特別講演>「地域をつくるホスピス運動~世界に学ぶ~」インド・ケララ州の取り組みを発表
特別講演では、インド南部のケララ州で20年ほど前から専門家とボランティアによる地域緩和ケアの仕組みづくりに取り組んできた、ケララ緩和ケア研究所代表のスレッシュ・クマール医師が活動を紹介。
また、ケララ州での取り組みを受けてイングランドで広がる緩和ケアのムーブメントについて、国際医療福祉大学大学院堀田聰子教授が講演した。
2人の講演の概要を紹介する。
【講 演1】「地域を作るホスピス運動」
【講 師】ケララ緩和ケア 研究所代表 スレッシュ・クマール氏
現在インドの人口は12億人超と、世界の人口の6分の1を占めている。年間およそ900万人が死亡し、約540万人が緩和ケアを必要としていると言われるが、十分な緩和ケアを受けられるのはそのうちの3%だ。
ケララ州は、人口だけを見るとインド全体の3%にしか満たない小さな町。しかし、インド国内にある緩和ケア施設約1500カ所のうち、87%に上る約1300カ所が、このケララ州内に集中している。
その理由として、コミュニティーアプローチによる緩和ケアのモデルプログラムを作り、実践してきたこと、さらにこのプログラムが非常に有効であることが言えるだろう。
緩和ケアには医師や看護師による医学的ケアなどがあるが、われわれのプログラムは、これに加えて、地域で緩和ケアに関する訓練を受けたボランティアのネットワークがあるのが特徴だ。
地域に緩和ケアに興味がある人がいれば、トレーニングを受けてもらう。基礎訓練は3時間。緩和ケアとは何かや患者とのコミュニケーションの基礎などを学ぶ。
もっと学びたい人には12時間の訓練もある。選択は本人次第だが、12時間の訓練を終えた人は、毎週最低2時間、近所の緩和ケア施設や在宅で、寝たきりの人や死を目前にした人のためにボランティア活動をしてもらう。
訓練を受けてもボランティアに参加しなければいけないということはない。しかし、学べば自分の家族や職場の同僚が病気になった時などに役立つ内容だ。
これまで5000人以上のボランティアがサービスを提供した。現在は学生たちがボランティアに多数関わってくれる。死にゆく人をケアすることは、ケアされる人にとっても、ケアする人にとっても、自分が変わる体験だ。活動は人が本来持つ思いやりの心を掘り起こし、育てる。やがてその活動を通じて、地域が、互いを思いやるコミュニティーに成長するのだ。
【講 演2】「Compassionate Communities (思いやりに満ちたコミュニティー)ムーブメントに学ぶ」
【講 師】国際医療福祉大学大学院教授 堀田 聰子氏
「健康は、医療職だけのものではなく、地域のわれわれすべてが責任を持って作り出していくもの」という健康への考え方は、1970年代に始まった。90年代に世界各地に広がり始め、WHO(世界保健機関)もその重要性を指摘する。
その新たな考え方を、緩和ケアにも応用しては、というアプローチが90年代に始まった。「生老病死に関わる問題をわれわれ地域住民に取り戻す」というものだ。
イングランドのいくつかの都市では、先ほどのインド・ケララ州でクマールさんに取り組みを学び、影響を受けた方々が中心になって、緩和ケアを身近なものにするため「思いやりのあるコミュニティー」をつくる動きがある。
地域住民が自分たちで地域の緩和ケアサービスや健康について調査し、考え、ボランティアを育成する活動で、世代を超えて広がっている。
イングランド北部のブラッドフォード市では、行政も一緒になって思いやりに満ちたコミュニティーをつくるためのキャンペーンもしている。
私はイングランドの現地調査や、その情報発信をしている。日本でも、より人間的な生き方、死に往き方を自分たちの手に取り戻すために何ができるのかを考えながら、今後も活動を続けたい。
【赤ひげフォーラム】日本のホスピス・在宅ケアの向かうべき方向は?
2月4日には、座長とシンポジストの計5人が全員、日本医師会赤ひげ大賞受賞者の「赤ひげフォーラム『日本のホスピス・在宅ケアの向かうべき方向は?』」が開かれた。シンポジストがそれぞれの長年の取り組みを語った後、参加者からの質問に答えた。
座長=二ノ坂保喜(にのさかクリニック院長/第3回赤ひげ大賞受賞)
シンポジスト=西嶋公子(医療法人社団公朋会理事長・社会福祉法人創和会理事長/第3回赤ひげ大賞受賞)、鬼頭秀樹(上那賀病院院長/同)、古川誠二(パナウル診療所所長/同)、土川権三郎(丹生川診療所所長/第4回赤ひげ大賞受賞)
東京都町田市の新興住宅地で、40年近く地域のファミリードクターとして外来診療と訪問診療に取り組んできた西嶋公子・医療法人社団公朋会理事長/社会福祉法人創和会理事長は、地域の女性たちが介護で疲弊する姿や自身の両親の様子から、家族での介護の限界を感じたと回想。地域で住民の参加を呼び掛けながら在宅ケアシステムを構築してきた様子などを語った。
徳島県那賀町町立上那賀病院の鬼頭秀樹院長は、同院の看取りの現状について発表。2006年1月から2016年7月に同院医師が死亡確認した600例を見ると、施設での看取りが急速に増加。施設での看取りは超高齢者、女性、老衰による死亡が多く、在宅での看取りは40代の若年も含み、男性、悪性疾患による死亡が多数を占めたとした。
さらに、看取った患者と家族の例を挙げながら、「忘れてはならないのは人が心から望む終末期医療とは、その人の心の中にあるものだということ。何らかの価値観で外部から強制されるものであってはならない」と強調した。
また、与論島のパナウル診療所の古川誠二所長は、「与論島の死生観と在宅医療」と題して講演。与論島で約20年診療に当たってきた経験と、土葬から火葬に変わり葬儀場ができたここ10年の島内の変化を語りつつ、「与論島の人は、自宅死以外を異常死と考える。現在でも在宅死が5割に上る背景には、伝統的な死生観が残っている」と説明。
人口約4400人、高齢化率30.5%の岐阜県高山市丹生川町で、外来、訪問診療・訪問看護などに取り組む土川権三郎・丹生川診療所所長は、10年ほど前から地域包括ケアシステムづくりに取り組んできた過程を紹介し、さまざまな職種が連携しての地域での在宅緩和ケアの体制づくりにも、手ごたえをにじませた。
【シンポジウム質疑より(一部)】
―まちづくり、地域づくりをする中で、心掛けていることは。
古川 地域というものは、できるだけそこの文化を守りながらゆっくり変わっていってほしいと思っている。その点でいうと今、「地域包括ケア」と騒がれ、一気にその方向に進んでいくことを心配している。医療者は、もっと謙虚に、そこに暮らす人たちの文化と生活を中心に考え、医療や地域づくりに関わる必要があるだろう。
西嶋 住民参加型でまちづくり、サービスづくりを進めてきた。大切にしたのは、誰でも参加できる仕組みを作ること。そのために繰り返しアンケートを取り、私自身も医師としてではなく、一住民として参加した。ケアセンター設立時には、ボランティアグループがパッチワークでベッドカバーを作ってくれた。「参加」を大事にした仕組みづくりが、どこの地域でも大事だと思う。
二ノ坂 大事なことの一つは、住民の主体性。地域包括ケアという言葉を、ケアを受けるお年寄りが知っているのか、どのぐらい理解しているのかということが大事ではないかと思う。さらに言えば、高齢者のためのケアだけではなく、地域住民みんなにとってのケアであることが大切だろう。「赤ひげ大賞」受賞者はみんな、長年にわたり、みんなの力を集めながら活動してきていると思う。医療者は往々にして、この人の生活を、生命を、医療が支えると思いがち。でも、在宅医療に取り組んでくると、生活全体の中に私たちの医療があるという当たり前のことに、改めて気づかされる。
―在宅ケアや終末期医療などで厳しい状況にある際、患者や家族を「救う」ということをどうとらえたらいいのか。
鬼頭 患者の家族の強い願いで、延命治療を施した際には、そのご家族のぶれない思いに打たれる一方、心の中に迷いもあった。「救う」にはどうしたらいいのかということは、一概に言えることではない。いろいろな状況を考え、患者さんやご家族のお話を十分聞いた上で、判断しなければいけないと思う。ただ、医療費の問題だけで決めることはあってはならない。
古川 与論島の人は、自然とともに生きている。死期を悟り、亡くなるまで自宅で過ごす。亡くなる一週間ほど前には「そろそろ自分はさよならするよ」と家族に話をし、亡くなる前日まで通常と変わらぬ様子で過ごし、食事をとる。私が緩和ケアの勉強をして、「こうすればどうか」などと勧めてみても、痛みをほとんど訴えず(投薬なども)受け付けない。これは、日本人がもともと持っていた能力で、今はさまざまな要因で奪われたものなのかもしれない。自分の人生や病気をどうとらえ、病気とともにどう暮らすのか。それをもう一度考え直すときではないか。へき地や離島の人の暮らしの中に、そのヒントがある。
土川 医師が自らの持つ知識や経験を含めて、患者や家族にきちんと説明することが必要だろう。患者や家族の中には、「病気になったら入院をして点滴をし、延命をするのが当然」だと思っている人がいる。それが当たり前だから、希望する。その間違った知識や習慣についてはしっかりと話をしなければならない。その上で、患者・家族とよく相談する。それを繰り返すしかないのだと思う。
西嶋 ターミナルは、本人と家族が納得いく時間を過ごせるかにかかっている。医療者は、それぞれの方の大事な時間をどうサポートできるかがポイントだ。長年関わってきて、今たどりついているのは、「ホスピスケアはグリーフケアに尽きる」ということ。亡くなっていく人は、亡くなった時点で身体的な苦痛などがなくなり、ピリオドが打たれる。一方で遺族は残りの寿命を生ききらないといけない。私が外来診療を続けているのは、外来に遺族の方がお見えになるから。立ち直っていく過程を見て、サポートしていかなければならないと思っている。